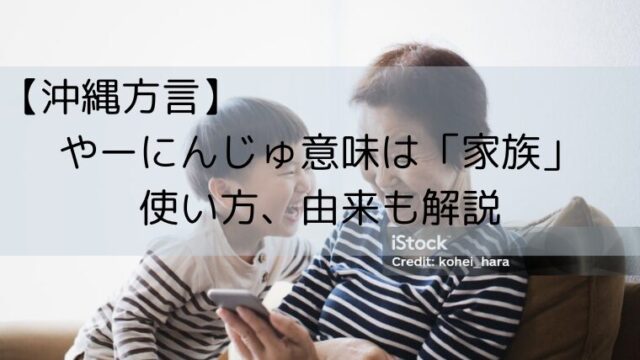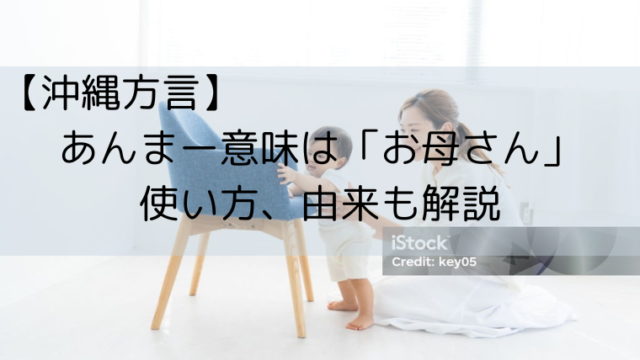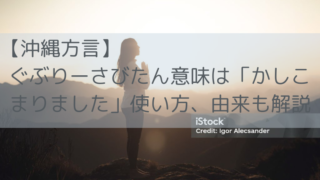皆さんのお住まいの地域で使われている方言では「お父さん」はどのような言い方でしょうか。
おとん、とと、おっとう、父ちゃん、親父、と色々な言い方があって面白いですよね。各地域でそれぞれ「お父さん」への言い方があるとは存じます。
今回の記事では沖縄方言の「お父さん」という方言に注目して解説していきたいと思います。
「おとう」の意味と使い方を徹底解説

皆さんの親御さんの一人、お父さんと呼ばれる人物ですが、沖縄では自身の父親を「おとう」や「たーりー」と言います。この記事では「おとう」で統一します。
では「おとう」の由来とは?日常会話で使うのか?を解説していきます。
おとうの意味、由来は?
「おとう」という言葉の由来はどこから来たのか、今から解説していきます。
まず、父という形は「おの+又(手)」で、手に石おのを持って打つ姿を示していて、斧フ(おの)の原字となります。
もと拍(うつ)と同系であり、成人した男性を示すのに、夫(おとこ)という字を用いたのですが、のちに父の字をおとこの意に当てることで、細分して父は「ちち」を、夫は「おとこ、おっと」を表すようになりました。
また、甫を当てることもある。覇ハ(おとこの長老)伯(長老)もこれと同系になります。
おとうの具体的な使い方を解説
さて、次は「おとう」という方言を使う場面・使い方について解説していきます。
きっと皆さんの想像している通りの場面で使われているのではないでしょうか。
沖縄の若い人は「おとう」を使う?

沖縄県では戦後に「標準語励行運動」が実施されたことはご存じでしょうか。伝統的な言葉の衰退が加速し、沖縄方言の衰退の主な要因が近年の核家族化です。
若者は年配の人と接する機会が減り、沖縄方言を話す・聞くことも少なくなっているのだそうです。
「おとう」を使う場面はいつ?どんなとき?
「おとう」の具体的な使い方は言わずもがな、父親に対して使うのですが、他の用途で使うとなると思い浮かびませんね。
後は日常会話で「自分のおとうが~」「あの人のおとうは~」と言うくらいではないでしょうか。
今の若いひとたちはおとうは使わない?
沖縄方言自体、現代の人たちはあまり使うことがないそうです。
他県からの移住者や沖縄本島の都市化、学校の授業で標準語の推進など様々な理由から沖縄方言を使う機会が減りつつあります。
「方言は大事」「しまくとぅばで話せるようになりたい」と沖縄の若者から声が挙がるも、「共通語を使うことが多く、方言を使う機会はない」「県外からの移住者もいるため(理解されにくい)方言は使いづらい」と現実を訴える声も多いです。
県はそのような沖縄方言衰退阻止への取り組みを行っています。
おとうを使う年代や地域
2013年に沖縄県が行った「しまくとぅば県民意識調査」によると、県民の8割の人々が「しまくとぅば」に親しみを感じている一方で、「日常的によく話している」県民は全体で3割程度。なかでも10代〜40代の県民では5%にも達していないそうです。
さらに「しまくとぅばでの会話内容を理解できるか」についても同様です。「よくわかる」と答えた人は40代で13.1%、50代では36.9%と、わずか10歳ほどの差にもかかわらず、「しまくとぅば」の認識に大きな差があることがわかっています。
「おとう」が使われている映画やドラマのタイトルやシーン
「おとう」が使われている映画やドラマのシーンはありませんでした。
「おとう」に関する新たな情報が入り次第情報を更新します。
「おとう」は店名などにも使われている
お店の名前で使われている事例
「おとう」が使われている店名はありませんでした。
「おとう」に関する新たな情報が入り次第情報を更新します。
お土産で使われている事例
「おとう」が使われているお土産はありませんでした。
「おとう」に関する新たな情報が入り次第情報を更新します。
その他で使われている事例 ※ATMのメッセージ、工事の看板など
「おとう」が使われているその他の事例はありませんでした。
「おとう」に関する新たな情報が入り次第情報を更新します。
「おとう」にまつわるエピソード
「おとう」にまつわるエピソードはありませんでした。
「おとう」に関する新たな情報が入り次第情報を更新します。
まとめ
方言というのは聞いていると面白いですよね。方言というのは各地域によって様々で、歴史を遡ると「この方言はこんな由来から来ているのか!」「あの方言は標準語でそのような意味だったのか!」とはっとさせられて、勉強にもなります。
よくテレビで高齢の方々にインタビューしている番組等でやりとりしている番組を見ていると飛び交う方言に圧倒されてしまいますね。見ているだけならとても楽しいですが、いざ自分が方言を使おうとすると、今この場面で使って合っているのか不安になったりします。
そこはなんとなく雰囲気でわかっていけるので心配は無いかと思います。
沖縄方言だけでなく、私たちの地域に根強く残っている方言をこれからも守っていきたいですね。