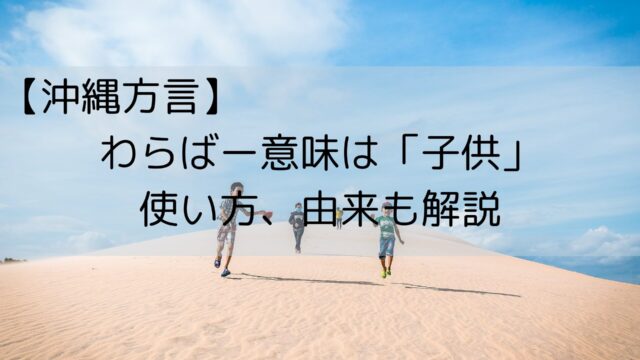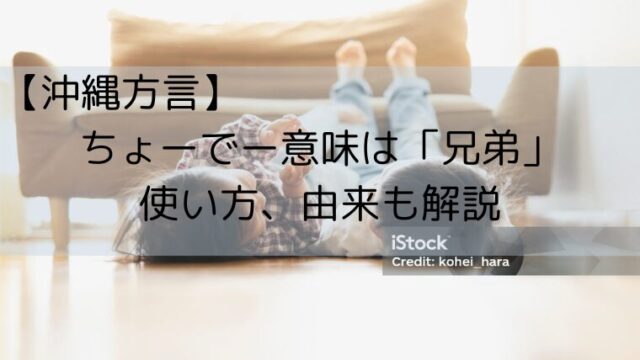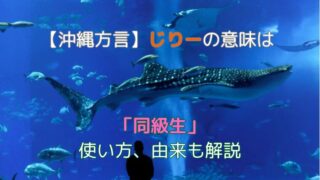社会人になると職場や普段の生活の中で、地元ではない人、つまり県外から引っ越して今ここで生活している人と接することが増えてきますよね。
自分自身も今の地へ他県から引っ越してきた方もいるかもしれませんが、出身地を聞くときにはだいたい「どちらの県の出身ですか?」と聞くと思います。「〇〇県の出身です」と答えがあれば「〇〇県の人なんですね」という流れになるでしょう。
沖縄の方言には「ないちゃー」といって、本土から沖縄に来た人とそうではない人を分けて使う言葉が存在します。
「ないちゃー」かそうではないか、なぜ分けて使っているのでしょうか。
今回は謎多き沖縄方言「ないちゃー」について解説していきます。
「ないちゃー」の意味と使い方を徹底解説

沖縄の方言の「ないちゃー」は、内地の人、沖縄以外の日本本土の出身者をあらわす言葉です。
沖縄に住む人たちといえば、地元愛に溢れて自分たちの文化や風習を大切にする人たちのイメージが強いですよね。
本土から来た人たちを良く思っていないという声も一部あることから、差別して使う言葉と思う方もいるかもしれませんが、使い方によっては反対に親愛の情を含む場合もあるそうです。
今回の記事を読めば、その見極め方についても知ることができますよ。
ないちゃーの由来は?
「ないちゃー」は「本土の人」という意味があります。
ないちゃーとは別に、本土の人に対して島ないちゃーと言うこともありますが、ないちゃーとの違いは”島(沖縄)に住む内地の人”、いわゆる本土から沖縄への移住者ということになるそうです。
また、沖縄に住む自分たちのことは「うちなんちゅ」と呼んでいます。ないちゃー、うちなんちゅという言葉で、自分たちと本土の人たちとを分けるために使っていたと考えられます。
しかし、今では「差別する・される」の感覚は小さくなってきており、沖縄県民とそれ以外の人を区別する言葉として使われることも多いようです。
ないちゃーの具体的な使い方、例文、返事を解説
先述したように「ないちゃー」は本土の人という意味を持ちます。
沖縄県外から届いた贈り物、「ないちゃーの友達が地元のプレゼントをくれた」
移住してきた人を褒める時に「ないちゃーだけど、沖縄料理がとっても上手」
旅行客に向けて「あなたはないちゃーですか?どこから来たの?」
うちなんちゅ(沖縄の人)と正反対の意味を持つないちゃーですが、使われることで少し相手と距離を感じてしまう方も、心配しなくて良い場合が多いことはぜひ覚えておいてくださいね。
沖縄の若い人は「ないちゃー」を使う?
実は「ないちゃー」は、沖縄の高齢者でもほとんど使わない言葉だそうです。
現在沖縄県民の中では、日常的に方言を使う人もいますが、標準語で会話する人も多くなってきています。その背景には、かつて学校教育で沖縄方言を禁止したり、マスメディアの影響により衰退してしまったといわれています。
今の若い人たちは「ないちゃー」は使わない
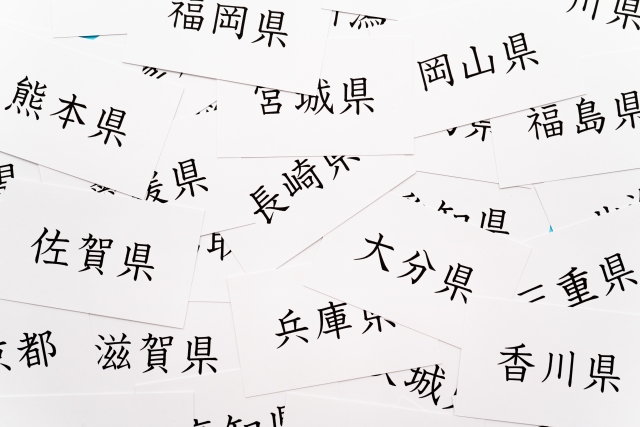
残念ながら、今「ないちゃー」は沖縄でもほとんど使われていません。
沖縄方言が「よくわかる」と答えた70代以上は54.0%に対し、10代はわずか0.4%という調査結果も出ており、現在ユネスコの消滅危機言語に認定されています。
つまり「ないちゃー」のみならず、うちなんちゅも沖縄方言から遠ざかってしまっていたのです。今あらためて、沖縄方言を守っていこうという活動も増えつつあります。
「ないちゃー」を使う年代や地域
高齢者は主に伝統的な言葉を多く使い、中高年はある程度標準語と沖縄方言を使い分け、若い世代は沖縄方言をほとんど使わず標準語を使う傾向があるようです。
高齢層(60代以上)は日常会話で沖縄方言を「主に使う、共通語と同じくらい使う」という回答が多く、中高年層(40代~50代)も、高齢層に次いで方言を使う割合が多いようです。
若年層(10代~30代)では、方言を使う割合は低いものの「ある程度必要」と感じる割合は増加傾向にあります。
沖縄県は9月18日を「しまくとぅばの日」とし、次世代に継承していくことを目的に2006年に制定しています。
「ないちゃー」が使われている映画やドラマのタイトルやシーン
「ないちゃー」がタイトルなどに使われている映画やドラマなどは見つかりませんでした。
「ないちゃー」に関する新たな情報が入り次第更新します。
「ないちゃー」は店名などにも使われている
店名などにも使われている事例
「ないちゃー」が名前に使われているお店などは見つかりませんでした。
「ないちゃー」に関する新たな情報が入り次第更新します。
お土産で使われている事例
「ないちゃー」が使われているお土産などは見つかりませんでした。
「ないちゃー」に関する新たな情報が入り次第更新します。
その他で使われている事例
「ないちゃー」が使われているその他の事例は見つかりませんでした。
「ないちゃー」に関する新たな情報が入り次第更新します。
「ないちゃー」にまつわるエピソード
沖縄の人々が「ないちゃー」を使うのには、その人の態度や行動によって警戒心や親愛の情などニュアンスが変わってきます。
戦後は本土からの開拓移民が大きな課題を残したとされています。
沖縄の復興と発展に貢献したとはいえ、新たな土地利用や環境問題、文化摩擦などが生じており、その当初の沖縄の人々からすると、「ないちゃー」を使う時に、差別的な意図をもって使うこともあります。
そのため移住者は自分が「ないちゃー」であることを自覚しながら葛藤を抱えることもあるようです。
しかし若い世代は、都会的なものへの憧れを込めて「ないちゃー」と呼ぶこともあるようです。
まとめ

沖縄の人々が差別的な意味を持って「ないちゃー」を使う背景には戦争が関係しています。
日本政府は1879年の琉球処分以降、沖縄の言葉や風習を「標準化」しようと試み、教育現場で方言の使用を禁止し、罰則として方言礼(ほうげんふだ)を使用しました。これは、学校で方言を使用した生徒にバツとして首から下げさせた木札のことです。
これを経験したり聞いたことのある沖縄の人からすると、本土の人間へ嫌悪感を抱いたり自分たちと呼び方をはっきり差別していたという複雑な想いも理解できます。
しかし今は、本土の人と地元の人を区別するだけの言葉に変わりつつあります。
どちらにしても、昔からある沖縄の「ないちゃー」という言葉が今後無くなることなく、若い世代の人が良い意味合いで「ないちゃー」を浸透してくれることが望ましいのではないでしょうか。