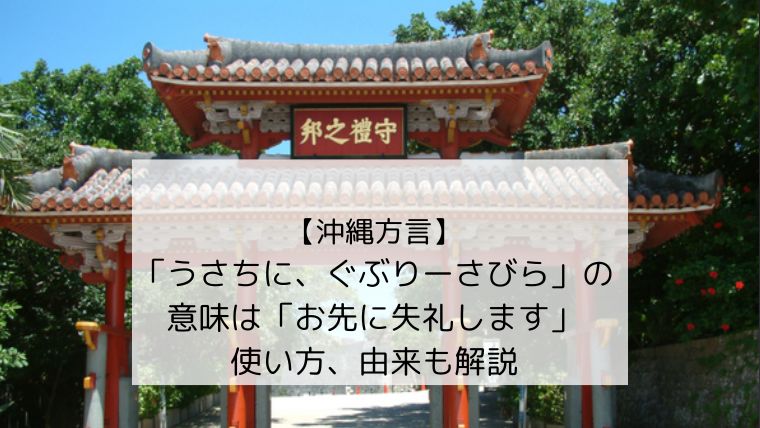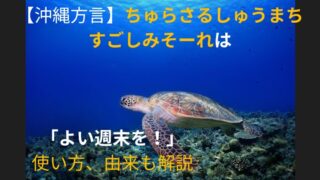皆さんは沖縄の方言にどのようなイメージをお持ちでしょうか?
柔らかくのんびりとした響きが特徴で、かわいらしさや親しみやすさを感じる人も多いようですね。
そんな沖縄の方言で「お先に失礼します」は何と言うのでしょうか?
沖縄は親戚が集まる年間行事が多数あり、また、沖縄の人は飲み会好きで仲間同士でよく飲み会を開催しています。飲み会をする口実として模合(もあい)という文化も一般的にあるくらい、気の合う仲間同士で集まって親睦を深める機会が多いので、「お先に失礼します」という挨拶も頻繁に使う機会があるはずです。
この記事を読み終わる頃には、きっとあなたも沖縄の居酒屋さんで「お先に失礼します」と方言であいさつができるようになっていることでしょう。それでは解説していきます。
「うさちに、ぐぶりーさびら」の意味と使い方を徹底解説

「うさちに、ぐぶりーさびら」の意味は「お先に失礼します」です。
実際に使う場合は「うさちに、ぐぶりーさびら」と言う場合と「さち、ないびらふー」と言う場合があります。「うさちに、ぐぶりーさびら」は敬語で、先輩やお年寄りの方など、目上の人に対して使います。そして、「さち、ないびらふー」は同級生や年下などに使う常体の言葉です。
実は、琉球王朝時代、沖縄は「守禮之邦(=守礼の国、しゅれいのくに)」といって、礼節を重んずる国でした。そのため、沖縄方言には数多くの敬語があり、同級生、年下に対して使う常体の言葉と目上の人に対して使う言葉がはっきり分かれています。
「さち、ぐぶりーさびら」の由来は?
「うさちに、ぐぶりーさびら」を分解して解説すると下記のようになります。
う:「お」=「御」で敬語を表す助詞です。この「う」は「さち」にかかります。
さち+に:「先+に」という意味を表します。
ぐ:「ご」=「御」で敬語を表す助詞です。この「ぐ」は「ぶりー」にかかります。
ぶりー=「無礼」という意味を表します。
さびら=「します」という意味を表します。
「さち、ぐぶりーさびら」の具体的な使い方、例文、返事を解説
模合で話が弾み、時間を忘れていた頃、家族から電話がかかってきて・・・
A:はい、もしもし~?
B:お母さん、いつ帰ってくるの?
A:あい!もうこんな時間ねー!?今帰るよ!
A:すいません、皆さん、うさちに、ぐぶりーさびら!
沖縄の人は「うさちに、ぐぶりーさびら」を使う?

最近では残念ながら「うさちに、ぐぶりーさびら」などの沖縄方言は一般的に使われていません。
現在、沖縄方言をきちんと使えるのは、80代の世代までで、中年層は聞き取りはできても話すことができないという方が多いです。
今の若い人たちは「うさちに、ぐぶりーさびら」は使わない
沖縄方言は、2009年にユネスコ(国際教育科学文化機関)により、消滅の危機に瀕する言語に指定され、沖縄県が平成25年度に行った調査において、その実態が明らかにされています。
「うさちに、ぐぶりーさびら」に限らず、若い世代は方言に接する機会が減少し、方言の担い手が地方にいないこともあって、方言離れが起きていると言われています。
現に、私は沖縄生まれ沖縄育ちの30代後半ですが、「うさちに、ぐぶりーさびら」を使ったことがありません。今年78歳の母も、14歳年上の伯母や祖母、同年代の仕事の同僚と話すときは方言を使っていますが、完全な方言ではなく、時々標準語、時々方言で話しています。
若い時は使っていたけれど、現在は使わなくなった言葉も増えてきているようで、「だんだん方言も忘れてきてるさー。使わなくなると忘れるんだよね。」と言っていました。
「うさちに、ぐぶりーさびら」を使う年代や地域

前述したように、「うさちに、ぐぶりーさびら」に限らず、若い世代は方言に接する機会が減少しています。そして、若い世代だけではなく、高齢の方でも「うさちに、ぐぶりーさびら」を使わない人は多いです。
前述した私の母も、親戚の集まりで先に帰る時、大叔母や父方の祖父母に対しては「うさちに、ぐぶりーさびら」を使いますが、70代の母の従兄弟達に対しては「先になろーねー(先に帰ろうね)」という微妙な標準語を使います。
「うさちに、ぐぶりーさびら」が使われている映画やドラマのタイトルやシーン
「うさちに、ぐぶりーさびら」がタイトルなどに使われている映画やドラマ等は見つかりませんでした。
「うさちに、ぐぶりーさびら」に関する新たな情報が入り次第更新します。
「うさちに、ぐぶりーさびら」は店名などにも使われている
お店で使われている事例
「うさちに、ぐぶりーさびら」がお店の名前に使われている事例はありませんでした。
「うさちに、ぐぶりーさびら」に関する新たな情報が入り次第更新します。
看板で使われている事例
「うさちに、ぐぶりーさびら」が看板に使われている事例はありませんでした。
「うさちに、ぐぶりーさびら」に関する新たな情報が入り次第更新します。
「うさちに、ぐぶりーさびら」にまつわるエピソード
今回の記事を書くにあたっての母との会話
今回は私の体験談について書こうと思います。
沖縄生まれ沖縄育ちの私ですが、30代後半の私でも、方言は使ったことがありませんし、分かりません。
しかし、沖縄方言が消滅の危機に瀕する言語に指定されていると知り、それなら勉強して紹介してみようと思い立ちました。そこで、とりあえず聞いたことがある言葉から書いていこうと、いろいろ方言を思い出していると、つい先日シーミー(清明)で親戚が集まったときに聞いた「うさちに、ぐぶりーさびら」が浮かびました。
私は方言を使わないので、うろ覚えで、ネット検索で「沖縄 方言 お先に失礼します!」を調べたら「さち、ぐぶりーさびら」とあり、「そっか、確か母もこう言ってたかなぁ」とさっそく母に「さち、ぐぶりーさびらの意味ってさぁ、お先に失礼しますで合ってる?」と聞くと笑われました。
「あんた、それ常体と敬語が混じっていて変だよ!?“さち”は常体で“ぐぶりーさびら”は敬語。統一しなきゃ!敬語として紹介するなら“うさちに、ぐぶりーさびら”で常体として紹介するなら“さち、ないびらふー”にしたほうがいいよ。標準語だって、“先、失礼します”って言わないじゃん。」と教えてもらいました。
最初から母に直接聞けばよかったな、そして中学校の国語教師をしていた母らしいな、と思いました。
まとめ
沖縄方言には数多くの敬語があり、同級生、年下に対して使う常体の言葉と目上の人に対して使う言葉がはっきり分かれています。
そして、沖縄は目上の人を敬うことを大切にする思想が強いため、挨拶の言葉もお年寄りを気遣う意味合いが強い言葉がたくさんあります。
私はてーげー(おおざっぱ)な性格なので、あまり気にしていませんが、沖縄の文化やスピリッツを大切にしていて、アイデンティティーの中に「私はうちなーんちゅ(沖縄人)だ」という想いを強く抱いている中学校の国語教師でもあった母にとっては「方言を継承していくのは良いことだけど、正しい言葉を伝承してほしい。沖縄の方言は常体と敬語をはっきり区別しないといけないし、武家出身の人と農民だった人が使う言葉も全然違うし、地域によっても言葉やイントネーションが全然違う。」と言われ、今回の記事執筆を通して沖縄方言を守り、次の世代へと伝えていくことの課題が見えてきました。
しかし、最初からそのように細かく考えていると、堅苦しくなってしまうので、まずは方言に触れて、親しみを持ってもらうことが重要ではないかと私は思います。
だから、皆さんも最初は敬語とか常体とか、あまり考えすぎず、「うさちに、ぐぶりーさびら」「さち、ないびらふー」のどちらでもいいので、気軽に使ってみてくださいね!