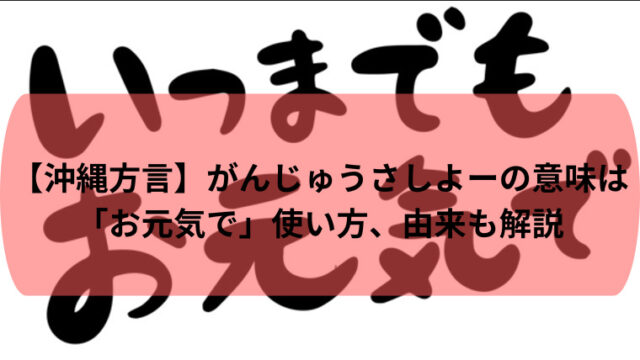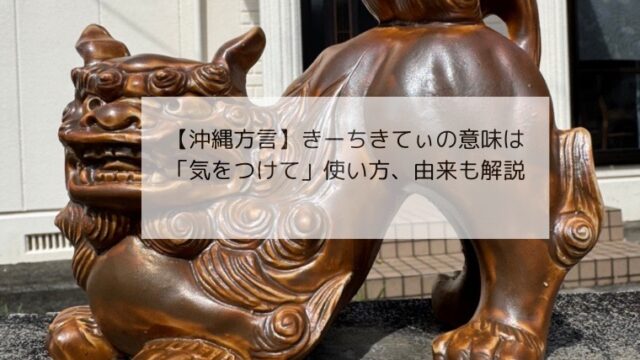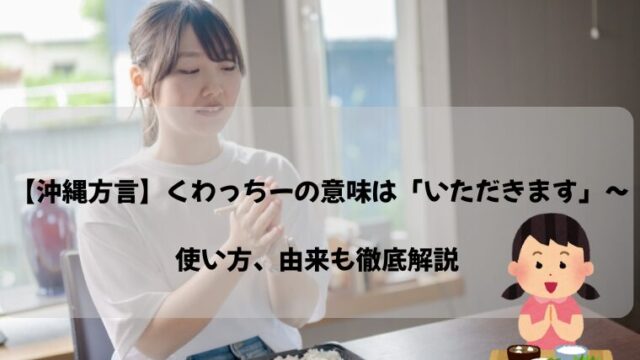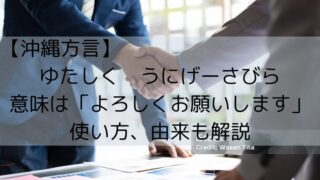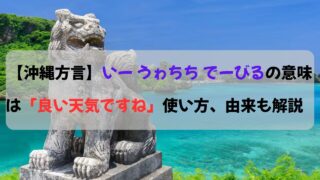花粉症と聞くと、鼻がムズムズしてくる人はいませんか?沖縄ではスギを植林してないので、花粉症の方はほとんど見かけません。
花粉症の時期になると、スギ花粉を避けるために旅行を兼ねて沖縄にくる人が増えてきます。沖縄の方言で、くしゃみをした人に対して「お大事に」という意味をもつ「くすけー」という言葉がありますよ。
「くすけー」という可愛らしい響きですが、日本語では「クソくらえ」の意味になるのには私自身びっくりしました。
もともとの言葉の意味は置いといて、今回は、「くすけー」=「お大事に」という表現について、深堀りしていきたいと思います。
「くすけー」は相手を思いやる素敵な言葉です。ちなみに、英語では、くしゃみをした時は「(God) bless you」=「お大事に」と言われるようです。
「くすけー」の意味と使い方を徹底解説

体に異変があるときに思わずでるくしゃみ。「くすけー」=「お大事に」=「(God) bless you」=「(神の)ご加護を!」愛のある言葉ですね。
「くすけー」の由来は?
さて、ここでは、不思議な言葉「くすけー」の由来について説明していきますね。
「くすけー」という言葉の起源には諸説ありまして、マジムン(魔物)が魂を奪うために人間にくしゃみをさせているという説。また、くしゃみをした人の魂が抜けるのを待ち構えているマジムン(魔物)を追い払うための言葉、だとも言われています。
沖縄県立博物館のWebアーカイブには、「物知りな人間は、くしゃみをすると「くすけひゃー」というから、まぶい(魂)はとれない」と閻魔大王がうっかり幽霊に言っていたのを子供の父親が聞いていた、とありました。
「くすけひゃー」や「くすけー」となって、子供の魂をとられないための呪文のような言葉だったのです。
いつの時代にも、相手(特に小さい子)を思いやる言葉があったのですね。「くすけー」は呪文の言葉となって、大人に対しても、くしゃみをしたらなげかける愛のある言葉になっていました。
沖縄県立博物館のWebアーカイブに、「実際の話者の語り」、「方言バージョン」「共通語バージョン」、「音声記号バージョン」がありましたので、興味をもった方は、ぜひサイトを覗いてみてくださいね。
「くすけー」の具体的な使い方、例文、返事を解説
次に、「くすけー」の具体的な使い方、例文、返事を解説します。沖縄LOVEWebのサイトにわかりやすい例文がありましたので、紹介しますね。
A:はーくしょ~ん!
B:くすけー(お大事に)(Bless you)
A:はくしょん、はくしょん、はくしょん、はっくしょん…
B:くすけー(お大事に)×(かける)100、(Bless you × 100)
A:ありがと (Thanks)
B:どういたしまして (You are welcome)
沖縄LOVEWebは、沖縄の人がハワイで体験した「くすけー」にまつわる実話がのってました。面白かったのでサイトをのせておきます。
沖縄の人は「くすけー」を使う?

今の若い人たちは「くすけー」は使わない
上記の沖縄県立博物館の方によると、50~60代ぐらいの方は言うかもしれないです。また、30~40代でおじいちゃんおばあちゃんからこの話を民話として聞いているかもしれない、との事です。
私自身は、民話自体を知らなかったので使ったことはありませんが、「くすけー」という言葉は聞いたことはあります。
今回いろいろと調べいくうちに、沖縄で若い人でも知っている人は、自然に使っていること。また、沖縄にきた観光客が「気になる沖縄の言葉」の一つとしてあげているのが多いとわかりました。
「くすけー」を使う年代や地域
「沖縄県しまくとぅば県民意識調査」では、宮古地域が最も高い使用率を示し、51.5%がしまくとぅばを日常的に使用しています。那覇市のある南部地域では使用率が最も低く、31.0%となっています。
沖縄県立博物館では、「くすけー」という表現は、おそらく沖縄本島、特に中南部では確実によく言ってる。北部でも言っているかもしれませんが、宮古島や八重山諸島は本島と違うとの事でした。
「くすけー」は店名などにも使われている
お店の名前で使われている事例
「くすけー」が店名に使用されている事例はありませんでした。
「くすけー」に関する新たな情報が入り次第更新します。
お土産で使われている事例
「くすけー」がお土産に使用されている事例はありませんでした。
「くすけー」に関する新たな情報が入り次第更新します。
その他で使われている事例
クスケーガーサ=サザナミヤッコ(魚)の名前の一部に「クスケー」がありました。キンチャクダイ科の魚です。参考までに写真を載せておきますね。

クスケーガーサの幼魚
 クスケーガーサの成魚
クスケーガーサの成魚
幼魚と成魚の模様が違う魚です。成魚は鱗全体がオリーブ色っぽい青で藍色の斑点がちらばります。
成長すると40cm程になり、お刺身などで食べたり、観賞用としても人気のお魚のようですね。
「くすけー」にまつわるエピソード

ものまね芸人「THEまねりーマン三上」さんのサイトに沖縄には不思議な言葉がいっぱいとありました。
『ある朝、会社でおっさんみたいなくしゃみをした時、「ハックショーンちくしょー!」と言ったら、女性社員の方が、「沖縄では『ちくしょー』って言わないんですよ!」。どうやら、沖縄ではくしゃみの後には「くすけー」というのが、「ちくしょー」の代わりの言葉となっているらしい』とありました。
そういえば、昔くしゃみにした後に「バカヤロー、チクショー」と言っていたおじさんがいませんでしたか?
私はTVドラマの中で聞いたような気がするのですが、それも「クスケー」と同じように、魂をとられないようにするための、呪文の言葉だったのかもしれないと妙に納得できたのです。
呪文の言葉は、大人になっても自分でも言いたくなりますよね。わかるような気がしました。
三上さん曰く、沖縄の不思議な言葉は挙げだしたらきりがないとも書いてましたよ。サイトを載せておきます。
まとめ

上のエピソードの他に、興味深いお話もありましたので、最後に紹介させていただきます。
徒然草の第四十七段に「清水詣りの尼がくしゃみをしたら「くさめくさめ」と言わないと死ぬといい、比叡山にいるぼっちゃんがくしゃみをしているかもしれないから唱えているのだ、世話していたぼっちゃんを思うと気が気でないから、まじないをしている」というお話です。
古来、日本ではクシャミの後にクサメクサメと口にする風習があったようです。くしゃみの語源が「クサメ」です。「クスケー」と少し似てますね。
「クスケー」に似ている表現や意味をもつ言葉が、徒然草の中にもあったことに驚いたと同時に、沖縄の方言の奥深さを知りました。
私も大切にしていこうと思います。
沖縄を訪れたさいに「クスケー」という言葉を聞いたら、「???」と思わずに温かい言葉なんだなと思ってください。きっと、心に染み渡る素敵な旅になることでしょう。